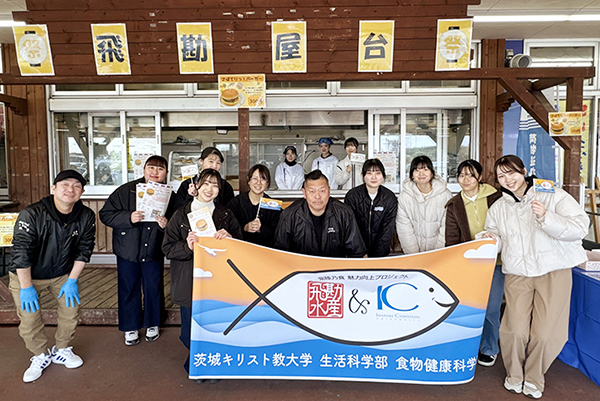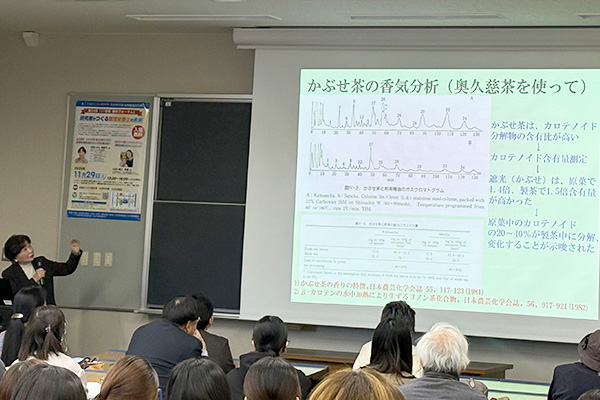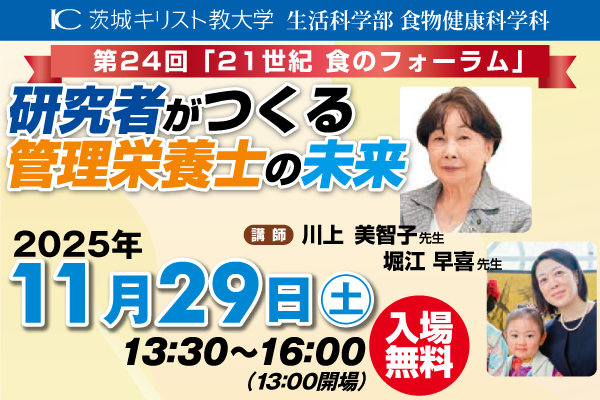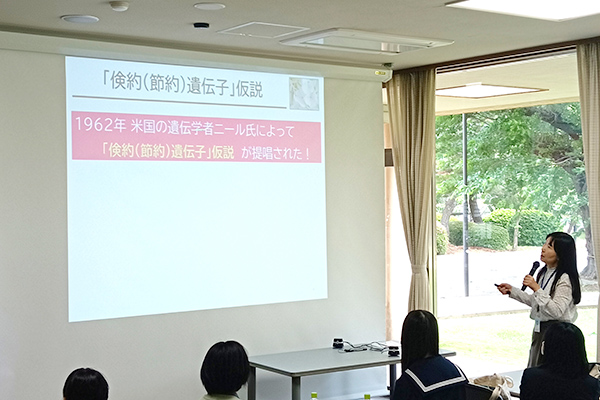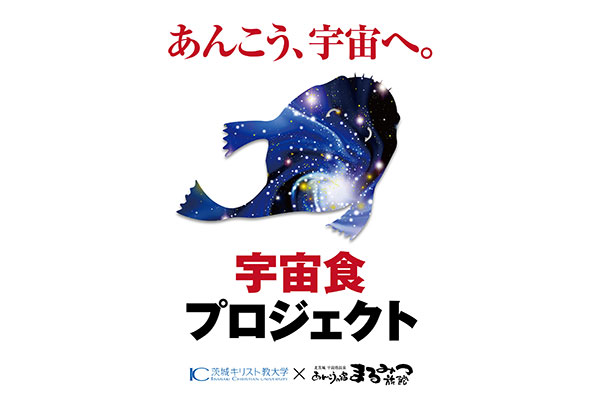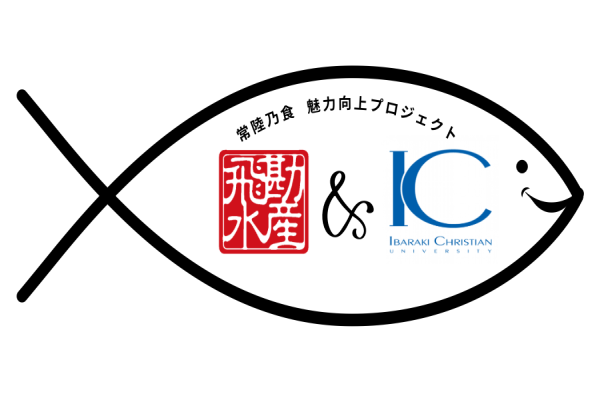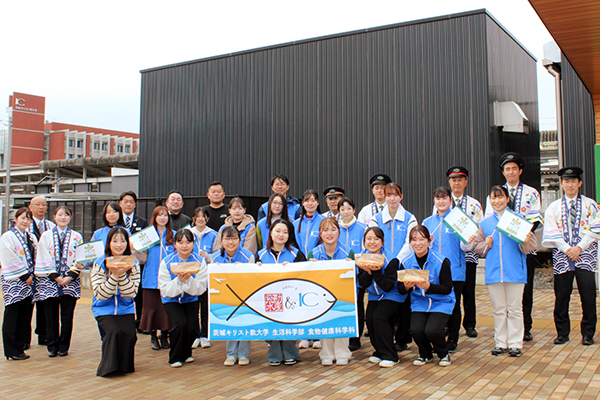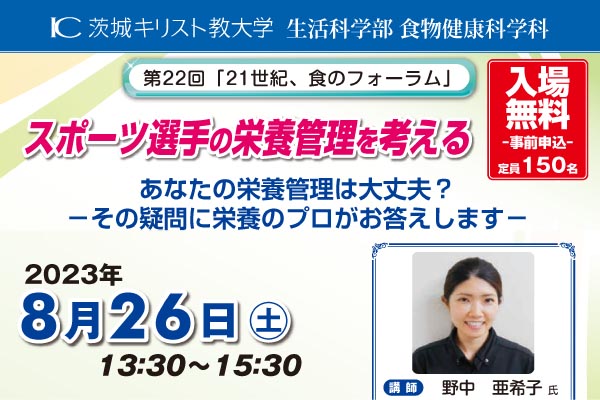![[生活科学部食物健康科学科]ヒトの健康と安全を守る、食のプロフェッショナルになる。](/academics/life/fod/tncui50000000mys-img/F_top.jpg)
![[生活科学部食物健康科学科]ヒトの健康と安全を守る、食のプロフェッショナルになる。](/academics/life/fod/tncui50000000mys-img/F_top.jpg)
食・栄養を通して人々の
健康づくり・疾病予防・重症化予防に
貢献する専門職を養成
人間が健康を維持するためには、栄養バランスに優れた適量の食事を規則正しく摂ることが基本です。食物健康科学科では、食事を通じて、心と体の健康を維持できるようにサポートする人材を育成します。カリキュラムは栄養、食の安全、食育に精通した食と健康の専門知識と実践力を養うことを目的として編成されています。実習・実験を行う学内の設備も充実。管理栄養士や栄養教諭はもちろん、公務員として働く行政栄養士やスポーツ栄養分野に関わるスタッフ、病院内の臨床栄養士、社会福祉施設の栄養士など、多様化する食と栄養の専門職のなかから希望する進路をめざせるような学びが可能です。
食物健康科学科の特徴
2025年度より新たな学び(カリキュラム)がスタートします
「スポーツ栄養学」や「食品開発論」、さらに高齢化社会にも対応できるように「在宅栄養管理学」といった魅力的な科目を新設しました。大学外で行われる実習(臨地実習)においては自らの学びに合わせて実習期間などが選択できます。例えば、医療に重点をおいた 3 週間の臨床分野の実習も選択可能です。
管理栄養士の多様な職務に対応した授業
傷病者に対する栄養管理を担う臨床栄養分野、地域社会で健康寿命の延伸などを図る公衆栄養分野、アスリートを支えるスポーツ栄養分野など、多様化する管理栄養士の仕事に対応できるよう専門的な学びが用意されています。希望する分野の学びを習得することで、卒業後に必要な実践力や即戦力が養われます。
教職をめざす学生への手厚いサポート体制
食物健康科学科では家庭科教諭(中学・高校)および栄養教諭の教職免許が取得可能です。教職課程では、食・栄養や家庭科に関する指導法を実践的に学ぶことができます。近年は教職支援センターの手厚いサポートによって、確かな成果が得られています。
食物健康科学科の学びについて
学びのポイント
管理栄養士として必要な知識や技術を、実験や実習を通して体系的に学びます。1・2年次は、基幹科目・専門基礎分野の科目を学び、栄養学の基礎を理解します。3年次以降は、専門分野の科目や臨地実習を経験し、応用力を養います。4年次の卒業研究では、さまざまな分野についてより理解を深め、探究していきます。取得資格
- 管理栄養士国家試験受験資格
- 栄養士
- 栄養教諭一種
- 中学校教諭一種(家庭)
- 高等学校教諭一種(家庭)
- 食品衛生監視員(任用)
- 食品衛生管理者
- 学校図書館司書教諭
- 社会福祉主事(任用)
中嶋 えりな さん
食物健康科学科 4年
茨城キリスト教学園高校 出身

大内 愛香 さん
食物健康科学科 4年
茨城県立 水戸第三高校 出身

カリキュラム
1年次
- 基幹科目
-
生化学Ⅰ 食品学Ⅰ
基礎演習
- 専門基礎分野
-
生化学Ⅱ 食品衛生学
調理学 食品学実験
調理学実習Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学Ⅰ・Ⅱ
解剖生理学実験Ⅰ
有機化学
食文化論 食品化学
- 専門分野
1.管理栄養士入門[1年次]
管理栄養士と栄養教諭の具体的な仕事の内容を学び、それぞれの職業に求められる倫理観や使命、社会的な役割などを理解します。授業では基礎的な知識を習得したうえで、グループで討論。さらに医療や教育など分野別に、業務内容や関連する職種との連携について理解を深めます。
2年次
- 基幹科目
-
基礎栄養学 公衆衛生学Ⅰ
栄養統計処理
- 専門基礎分野
-
食品学Ⅱ(食品加工学を含む)
公衆衛生学Ⅱ 病理学
医学一般Ⅰ 有機化学
食文化論 食品化学
- 専門分野
-
給食経営管理論Ⅱ 1.給食経営管理実習Ⅰ・Ⅱ
臨床栄養学Ⅰ・Ⅱ 臨床栄養学実習
公衆栄養学Ⅰ・Ⅱ 2.栄養教育論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
ライフステージ栄養学Ⅰ・Ⅱ 生活経営論
生活経済学 保育学 児童臨床学
衣服環境論 居住環境論

2.給食経営管理実習Ⅰ・Ⅱ[2年次]
給食の運営計画から実施・評価・改善までの一連の流れ(給食経営管理)を学びます。学生自ら栄養バランスや価格を考慮した献立作成を行い、作業工程を計画し、大量調理を実施します。給食提供時には、献立の栄養成分表示やポスターを掲示し、栄養に関する情報提供を行います。
3.栄養教育論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ[2年次]
栄養教育に必要な知識やスキルを習得します。Ⅰでは、栄養教育の定義と歴史、栄養教育に必要な理論、さらに栄養教育の計画、実施、評価の方法を学び、科学的根拠に基づく栄養指導ができるように知識の獲得をめざします。Ⅱでは、Ⅰで学んだことを基に演習を行い、栄養教育実践のスキル獲得をめざします。Ⅲでは、栄養教育の際に必要なカウンセリング技法を身につけ実践できる力を養います。
3年次
- 基幹科目
-
総合演習Ⅰ・Ⅱ
- 専門基礎分野
- 専門分野
-
栄養学実験 臨床栄養学Ⅲ・Ⅳ
公衆栄養学実習 栄養教育論実習
2.応用栄養学実習 3.応用臨床栄養学実習
学校栄養指導論Ⅰ・Ⅱ 国家試験対策演習Ⅰ
臨地実習Ⅰ(給食の運営) 臨地実習Ⅱ(給食経営管理)
臨地実習Ⅲ(公衆栄養) 臨地実習Ⅳ(臨床栄養)
臨地実習Ⅴ(臨床栄養)
スポーツ栄養学 災害栄養学(演習を含む)
子どもの食と栄養 食品開発論
在宅栄養管理学 マーケティング論(演習を含む)
嚥下と口腔ケア 子どもの食と栄養 保育学 児童臨床学
衣服環境論 居住環境論
1.運動栄養生理学実験[3年次]
講義科目である「運動生理学」で学んだ知識を踏まえ、運動によって生じる身体の変化について実験します。運動時と安静時、それぞれにおいて実験を行い、得られたデータを比較・分析します。運動による身体の変化を体験的に理解したうえで、肥満者やスポーツ競技者など対象者に応じた体力評価方法や栄養管理について学修します。

2.応用栄養学実習[3年次]
子どもから高齢者まで、さらには女性の妊娠期といった人生のライフステージごとの栄養管理について、実践的に学びます。対象者の栄養評価や食事計画、献立立案、調理を行い、管理栄養士として必要な能力を習得します。

3.応用臨床栄養学実習[3年次]
医療機関で管理栄養士が行う栄養管理について、糖尿病や胃がんなど症例が多い疾患別に栄養管理の手法や技術を習得します。指導は医療施設で実務経験のある教員が担当し、医療・介護保険制度や事故が起きた際の報告などにもふれるなど、仕事の現場での実践に即した授業です。

資格取得に向けた学外実習スケジュール
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理栄養士国家試験受験資格 | - | - | 臨地実習Ⅰ(給食の運営) 給食施設 5日間 臨地実習Ⅱ(給食経営管理) 給食施設 5日間 臨地実習Ⅲ(公衆栄養) 保健所・保健センター 5日間 臨地実習Ⅳ(臨床栄養) 病院 10日間 臨地実習Ⅴ(臨床栄養) 病院 15日間 |
|
| 栄養教諭一種 | - | - | - | 栄養教育実習 茨城県内小・中学校 5日間 ※事前に1日観察実習あり |
進路・就職
卒業後の道
管理栄養士の活躍の場は、病院、福祉施設、保育所、給食委託会社、教員・公務員など、広範囲に及びます。大学で習得した専門知識を活用し、人々の健康を多方面からサポートしています。家庭科教諭や栄養教諭として食育に携わる道も開かれ、卒業生は食と栄養に関する専門職として地域・社会に貢献しています。めざせる職種・業界
- 管理栄養士
- 教員(栄養・家庭)
- 病院
- 保健所
- 市町村保健センター
- 社会福祉施設
- 保育所
- 食品関連企業
- 給食委託会社 など
就職実績(2025年5月1日現在)
- 卸売業、小売業(薬局・ドラッグストアなど)
- 医療、福祉
- 宿泊業、飲食サービス業(給食委託会社など)
- 教育、 学習支援業
- 公務
- 情報通信業
- 製造業
- その他
主な就職先(2025年3月卒業生)
- 北水会記念病院
- 常陸大宮済生会病院
- 瀧病院
- 水戸協同病院
- わかくさこども園
- 太田さくら認定こども園
- 社会福祉法人北養会 特別養護老人ホームもくせい
- (株)カスミ
- エームサービス(株)
- (株)グリーンハウス
- 富士産業(株)
- ウエルシア薬局(株)
- (株)カワチ薬品
- 東京フード(株)
- 日清医療食品(株)
- 筑波乳業(株)
- イトウ製菓(株)
- アイングループ
- 日立市立十王中学校(家庭)
- 川崎市立菅生中学校(家庭)
- 茨城県(管理栄養士)
- 土浦市役所(管理栄養士)
- 小美玉市役所(管理栄養士)
卒業生の声

実験や実習、グループワークが
今の私に育ててくれた
会田 さゆり 生活科学部 食物健康科学科 教員

大貫 和恵 生活科学部 食物健康科学科 教員
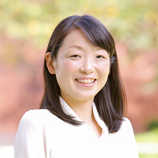

食物健康科学科の教員一覧
高度な専門性と、豊富な現場経験を兼ね備えた教員は、学生の飛躍的な成長を支える原動力。成績優秀なだけではない、他者に寄り添い支えられる、真に優れた人材の育成に向けて、大学全体でチームワークを組み、持てる力の限りを尽くして取り組んでいます。