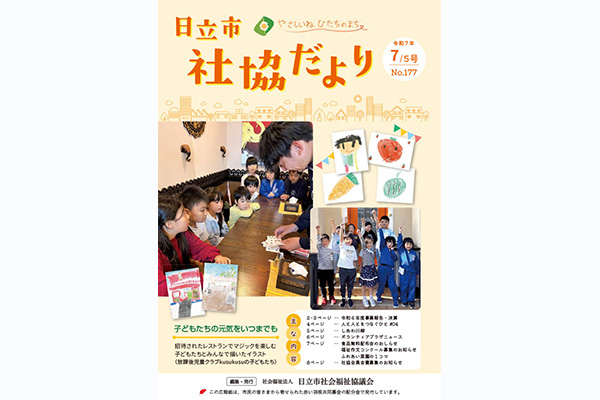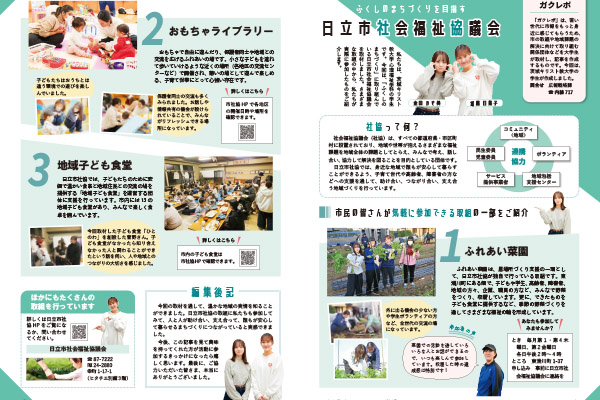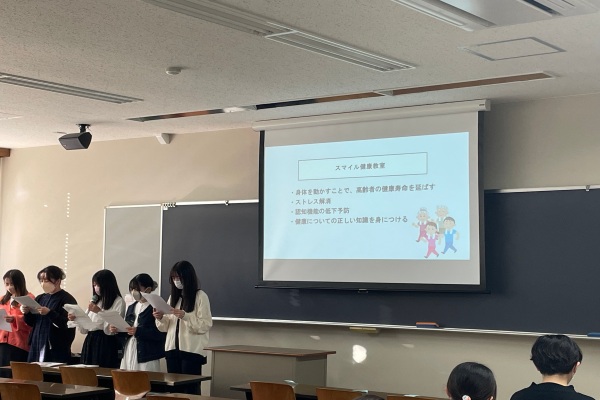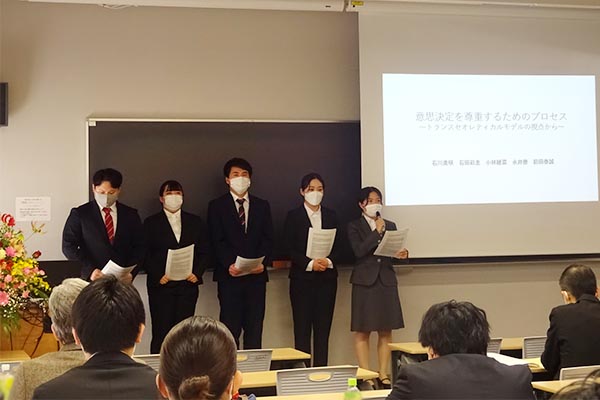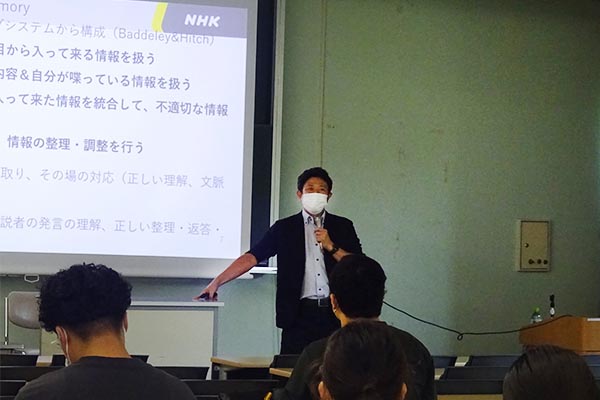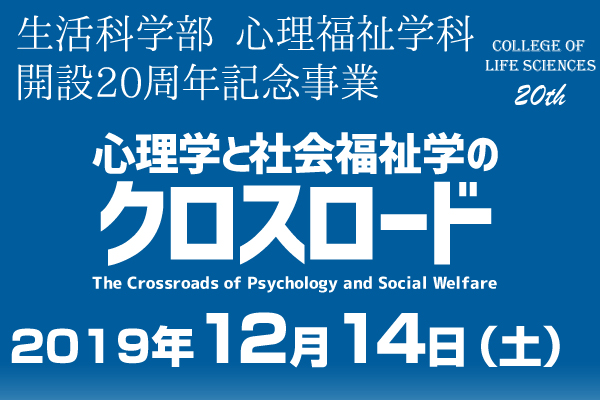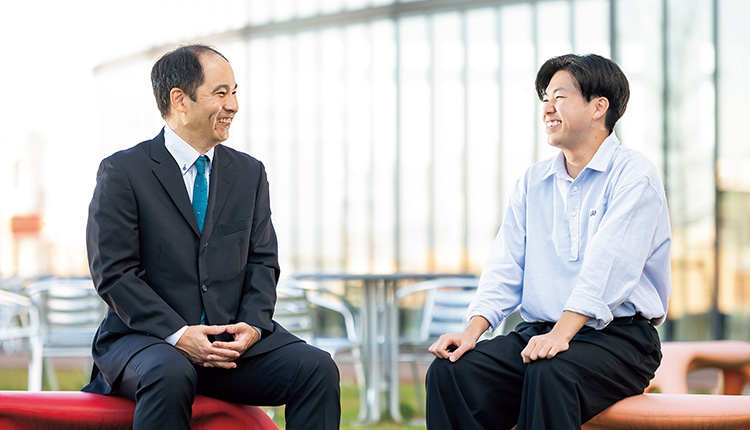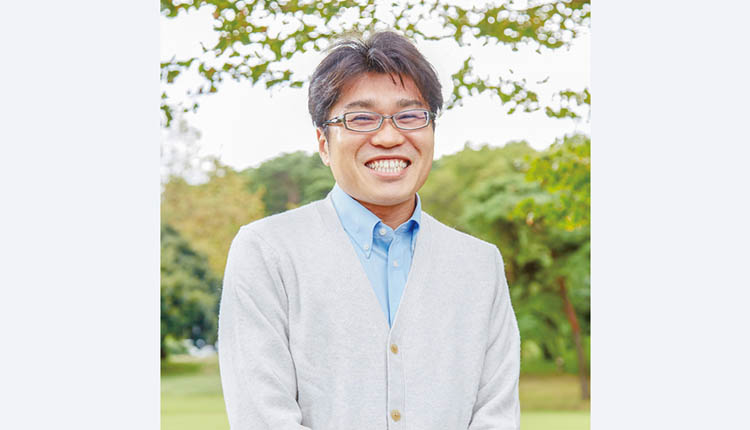![[生活科学部心理福祉学科]](/academics/life/wel/tncui50000000nb8-img/W_top.jpg)
![[生活科学部心理福祉学科]](/academics/life/wel/tncui50000000nb8-img/W_top.jpg)
心理と福祉を学び人間と社会を理解する
強みを持つスペシャリストを育てる
心理と福祉、2つの領域をバランス良く学び、両側面から人間と社会への理解を深めることができます。心理、福祉とも専門的な知識を習得するだけにとどまらず、充実した実習科目により理論を行動に移せる実践力も養うカリキュラムを編成しています。これにより福祉の制度や法律を理解した心理分野の専門職や、心理の側面から社会の課題解決にアプローチできる福祉職など、専門に加えて隣接する分野に強みを持つスペシャリストを育成します。
心理福祉学科の特徴
人を支える心理と福祉をバランス良く学ぶ
感情や性格など人のこころを学ぶ「心理学」と、福祉を取り巻く制度や法律、環境について考える「社会福祉学」。これらの2分野をバランス良く学びます。その後、学びの軸足をいずれかに定めつつも、両側面から人間や社会を理解します。
カウンセリング研究発祥の地。その実績を背景としたカリキュラム
ICの「カウンセリング研究室」は、日本のカウンセリング研究発祥の地。その実績を背景とするカリキュラムにより、カウンセリングや相談援助の技術を学び、こころの痛みに寄り添う姿勢も養います。
現場で即戦力となるソーシャルワーカーをめざす
福祉の学びでは、社会福祉制度の知識や相談援助技術などの実践的なスキルを身につけます。社会福祉士国家試験の受験に向けて教員が丁寧にサポート。国家試験の合格率は例年、全国平均を大きく上回っています。
ニュース
- 心理福祉学科:保護者懇談会、個別面談を開催しました 2024.12.12
- 心理福祉学科:保護者懇談会を開催しました 2023.12.07
- 心理福祉学科:保護者懇談会を開催しました 2022.12.17
- 心理福祉学科:共同研究を紹介します 2022.03.28
- 心理福祉学科:論文が掲載されました 2021.12.13
- 心理福祉学科:保護者懇談会を開催しました 2021.11.30
- 心理福祉学科:論文が掲載されました 2021.07.05
- 心理福祉学科:『2020年度 実習報告会』のご報告(2021年2月20日) 2021.03.02
- 心理福祉学科:「日本健康心理学会 第33回大会」発表報告 2020.11.23
- 生活科学部心理福祉学科「キャンパスの集い」が開催されました。 2020.07.07
- 生活科学部心理福祉学科のニュース配信を始めます! 2020.05.29
- 茨城キリスト教大学大学院生活科学研究科 心理学専攻説明会を開催します 2019.11.26
- 第30回社会福祉士国家試験合格発表・本学は新卒77.3%の合格率(全国平均30. 2%) 2018.03.15
- 第29回社会福祉士国家試験合格発表 2017.03.15
心理福祉学科の学びについて
学びのポイント
心理と福祉は、人をサポートするという点で共通します。これらをバランス良く学び、興味や目標に即して専門性を深めていけるカリキュラムを編成しています。福祉をよく知る心理のスペシャリスト、 こころを理解する福祉の専門職など、強みを持った人材を育成します。取得資格
- 社会福祉士国家試験受験資格
- 認定心理士
- 中学校教諭一種(社会)
- 高等学校教諭一種(公民)
- 高等学校教諭一種(福祉)
- 学校図書館司書教諭
- 社会福祉主事(任用)
めざせる資格
- 公認心理師国家試験受験資格
田口 大翔 さん
心理福祉学科 4年
茨城県立 多賀高校 出身

小林 朋矢 さん
心理福祉学科 4年
茨城県立 多賀高校 出身

橋本 菜穂子 さん
心理福祉学科 3年
茨城県立 水戸第三高校 出身

「心理・福祉」2つの学び

心理
人のこころについて、感情や性格などの成り立ちや発達、社会や環境からの影響を理解するとともに、こころの問題を抱える人に関わる技術を身につけるため、心理カウンセリング系科目を充実させたカリキュラムになっています。

福祉
社会生活を営むうえで、問題を抱えている人に手を差しのべる福祉制度や法律などを学ぶ福祉系科目。少子高齢化や経済的格差が深刻化する今、社会福祉士や各種のソーシャルワーカーなど、福祉系専門職の需要が高まっています。
カリキュラム
1年次
- 基幹科目
-
基礎演習Ⅰ・Ⅱ 社会福祉の原理と政策Ⅰ・Ⅱ
1.心理学概論Ⅰ・Ⅱ
- 専門基礎科目
- 心理カウンセリング系科目
-
心理学統計法 発達心理学 公認心理師の職責
- 福祉系科目
-
児童・家庭福祉Ⅰ・Ⅱ 障害者福祉Ⅰ・Ⅱ
高齢者福祉Ⅰ・Ⅱ ソーシャルワーク演習
- 心理福祉教育系科目
-
法学 生活と政治 生命と倫理 社会学
生活と国際経済 福祉教育論Ⅰ・Ⅱ
高齢者生活論 女性学 人権と教育 人間と哲学

1.心理学概論Ⅰ・Ⅱ[1年次]
初年次に開講する心理学の基本を学ぶ科目です。心理学が学問として成立し発展してきた経緯を理解したうえで、感覚、知覚、記憶、学習、思考、言語、発達、社会、臨床など幅広いテーマから心理学の概要を捉えます。そして人のこころの基本的なしくみや働きを理解し、心理系専門科目の学びにつなげていきます。
2.社会・集団・家族心理学Ⅰ・Ⅱ[1~2年次]
社会の中で生きる人の態度や行動を理解する社会心理学を学ぶ科目です。授業では日常生活で起こる現象を社会心理学の観点で分析し、より良い社会や対人関係の構築に役立てるため、Ⅰでは個人の内面に、Ⅱでは対人関係や集団にそれぞれ焦点を当て、人と社会の関係を考えていきます。

3.ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)[1年次]
ソーシャルワーク(相談援助)の専門職であるソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士)について基礎から学ぶ科目です。それらが形成された経緯、法的な位置づけ、その仕事や職業に託された理念や倫理、担う役割や課された規範などについて、動画資料を用いたり、グループワークを行ったりして理解します。
2年次
- 専門基礎科目
-
人間観と倫理A・B 1.社会・集団・家族心理学Ⅰ・Ⅱ
キリスト教福祉 心理福祉海外研修Ⅰ
臨床心理学概論 発展演習A・B
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク実習Ⅰ 心理福祉海外研修Ⅱ
愛と死の人間学 社会福祉発達史A・B
人体の構造と機能及び疾病
心理福祉特講A・B・C・D 神経・生理心理学
- 心理カウンセリング系科目
-
心理学統計法 発達心理学
公認心理師の職責 福祉心理学
健康・医療心理学 感情・人格心理学
深層心理学 心理検査法実習
精神疾患とその治療 関係行政論
障害者・障害児心理学 心理学研究法Ⅰ・Ⅱ
老年心理学 心理演習
学習・言語心理学 心理的アセスメント
2.知覚・認知心理学 教育・学校心理学
心理学的支援法 心理学実験Ⅰ・Ⅱ
- 福祉系科目
-
児童・家庭福祉Ⅰ・Ⅱ 障害者福祉Ⅰ・Ⅱ
高齢者福祉Ⅰ・Ⅱ ソーシャルワーク演習
ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク演習(専門)Ⅰ・Ⅱ
介護技術 介護概論
3.福祉サービスの組織と経営A・B
保健医療と福祉Ⅰ・Ⅱ 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ
社会福祉調査の基礎 ジェンダー福祉論
4.社会保障Ⅰ・Ⅱ ファミリーソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
貧困に対する支援 権利擁護を支える法制度
刑事司法と福祉A・B 医学概論
- 心理福祉教育系科目
-
法学 生活と政治 生命と倫理 社会学
生活と国際経済 福祉教育論Ⅰ・Ⅱ
高齢者生活論 女性学 人権と教育
人間と哲学 社会病理学 人文地理学Ⅰ・Ⅱ
自然地理学Ⅰ・Ⅱ 地誌
西洋史 日本史A・B 東洋史
1.社会・集団・家族心理学Ⅰ・Ⅱ[1~2年次]
社会の中で生きる人の態度や行動を理解する社会心理学を学ぶ科目です。授業では日常生活で起こる現象を社会心理学の観点で分析し、より良い社会や対人関係の構築に役立てるため、Ⅰでは個人の内面に、Ⅱでは対人関係や集団にそれぞれ焦点を当て、人と社会の関係を考えていきます。

2.知覚・認知心理学[2~4年次]
人が周囲の世界を感知する、いわゆる五感に関する授業です。目や耳、鼻や舌、皮膚から入ってきた情報を、脳はどのように処理をして外の世界を認識するかについてや、その過程とこころの働きの関連について理解します。さらに脳の情報処理が、加齢や障害によりどう変化するかについても学びます。
3.福祉サービスの組織と経営A・B[2~4年次]
社会福祉法人や医療法人、NPO法人などの社会福祉サービスを提供する組織の形態や機能を学びます。そのうえで、社会学・経営学の基礎理論に基づいた組織の基礎理論や集団力学・リーダーシップ理論や健全な経営を推進するための組織管理の方法への理解を深め、また財務諸表を読み解けるようにします。
4.社会保障Ⅰ・Ⅱ[2~4年次]
現代社会における生活とさまざまな社会保障の関わりを学びます。Ⅰでは医療保険制度と介護保険制度を中心に、Ⅱでは年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険、社会手当を中心に、各制度について歴史的経緯、現状、体系などの基本的な枠組みを理解したうえで、現在の課題を考えます。
3年次
- 基幹科目
-
心理福祉演習Ⅰ・Ⅱ
- 専門基礎科目
-
ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ ソーシャルワーク実習Ⅰ
心理福祉海外研修Ⅱ 愛と死の人間学
社会福祉発達史A・B 人体の構造と機能及び疾病
心理福祉特講A・B・C・D 神経・生理心理学
- 心理カウンセリング系科目
-
感情・人格心理学 深層心理学
心理検査法実習 精神疾患とその治療
関係行政論 障害者・障害児心理学
心理学研究法Ⅰ・Ⅱ 老年心理学
心理演習 学習・言語心理学
心理的アセスメント 1.知覚・認知心理学
教育・学校心理学 心理学的支援法
心理学実験Ⅰ・Ⅱ 司法・犯罪心理学
トランスパーソナル心理学 癒しのセラピー
産業・組織心理学 心理実習
- 福祉系科目
-
児童・家庭福祉Ⅰ・Ⅱ 障害者福祉Ⅰ・Ⅱ
高齢者福祉Ⅰ・Ⅱ ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク演習(専門)Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク演習(専門)Ⅲ・Ⅳ
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ・Ⅳ
ソーシャルワーク実習Ⅱ
介護概論 2.福祉サービスの組織と経営A・B
保健医療と福祉Ⅰ・Ⅱ 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ
社会福祉調査の基礎 ジェンダー福祉論
3.社会保障Ⅰ・Ⅱ ファミリーソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
貧困に対する支援 権利擁護を支える法制度
刑事司法と福祉A・B 医学概論
- 心理福祉教育系科目
-
社会病理学 人文地理学Ⅰ・Ⅱ 自然地理学Ⅰ・Ⅱ
地誌 西洋史 日本史A・B 東洋史

1.知覚・認知心理学[2~4年次]
人が周囲の世界を感知する、いわゆる五感に関する授業です。目や耳、鼻や舌、皮膚から入ってきた情報を、脳はどのように処理をして外の世界を認識するかについてや、その過程とこころの働きの関連について理解します。さらに脳の情報処理が、加齢や障害によりどう変化するかについても学びます。
2.福祉サービスの組織と経営A・B[2~4年次]
社会福祉法人や医療法人、NPO法人などの社会福祉サービスを提供する組織の形態や機能を学びます。そのうえで、社会学・経営学の基礎理論に基づいた組織の基礎理論や集団力学・リーダーシップ理論や健全な経営を推進するための組織管理の方法への理解を深め、また財務諸表を読み解けるようにします。
3.社会保障Ⅰ・Ⅱ[2~4年次]
現代社会における生活とさまざまな社会保障の関わりを学びます。Ⅰでは医療保険制度と介護保険制度を中心に、Ⅱでは年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険、社会手当を中心に、各制度について歴史的経緯、現状、体系などの基本的な枠組みを理解したうえで、現在の課題を考えます。
4年次
- 基幹科目
-
心理福祉演習Ⅲ・Ⅳ
- 専門基礎科目
-
卒業研究 愛と死の人間学 社会福祉発達史A・B 人体の構造と機能及び疾病 心理福祉特講A・B・C・D 神経・生理心理学
- 心理カウンセリング系科目
-
深層心理学 心理検査法実習
精神疾患とその治療 関係行政論
障害者・障害児心理学 心理学研究法Ⅰ・Ⅱ
老年心理学 心理演習 学習・言語心理学
心理的アセスメント 1.知覚・認知心理学
教育・学校心理学 心理学的支援法
心理学実験Ⅰ・Ⅱ 司法・犯罪心理学
トランスパーソナル心理学 癒しのセラピー
産業・組織心理学 心理実習
- 福祉系科目
-
児童・家庭福祉Ⅰ・Ⅱ 障害者福祉Ⅰ・Ⅱ
高齢者福祉Ⅰ・Ⅱ 社会福祉士試験対策講座Ⅰ・Ⅱ
ソーシャルワーク演習(専門)Ⅲ・Ⅳ
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ・Ⅳ
ソーシャルワーク実習Ⅱ 介護概論
2.福祉サービスの組織と経営A・B 保健医療と福祉Ⅰ・Ⅱ
地域福祉と包括的支援体制Ⅰ・Ⅱ 社会福祉調査の基礎
ジェンダー福祉論 3.社会保障Ⅰ・Ⅱ
ファミリーソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱ
貧困に対する支援 権利擁護を支える法制度
刑事司法と福祉A・B 医学概論
- 心理福祉教育系科目
-
社会病理学 人文地理学Ⅰ・Ⅱ
自然地理学Ⅰ・Ⅱ 地誌
西洋史 日本史A・B 東洋史

1.知覚・認知心理学[2~4年次]
人が周囲の世界を感知する、いわゆる五感に関する授業です。目や耳、鼻や舌、皮膚から入ってきた情報を、脳はどのように処理をして外の世界を認識するかについてや、その過程とこころの働きの関連について理解します。さらに脳の情報処理が、加齢や障害によりどう変化するかについても学びます。
2.福祉サービスの組織と経営A・B[3~4年次]
社会福祉法人や医療法人、NPO法人などの社会福祉サービスを提供する組織の形態や機能を学びます。そのうえで、社会学・経営学の基礎理論に基づいた組織の基礎理論や集団力学・リーダーシップ理論や健全な経営を推進するための組織管理の方法への理解を深め、また財務諸表を読み解けるようにします。

3.社会保障Ⅰ・Ⅱ[3~4年次]
現代社会における生活とさまざまな社会保障の関わりを学びます。Ⅰでは医療保険制度と介護保険制度を中心に、Ⅱでは年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険、社会手当を中心に、各制度について歴史的経緯、現状、体系などの基本的な枠組みを理解したうえで、現在の課題を考えます。

資格取得に向けた学外実習スケジュール
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉士国家試験受験資格 | - | ソーシャルワーク実習Ⅰ 福祉施設・病院 8日間程度 |
ソーシャルワーク実習Ⅱ 福祉施設・病院 24日間以上 |
- |
| 公認心理師国家試験受検資格 [注] |
- | - | 心理実習 医療施設等40時間以上(選抜することがあります。) |
- |
[ 注 ] :大学+大学院での学び、または大学+実務経験などが必要。
進路・就職
卒業後の道
卒業生は、医療や福祉の分野などで、人々をサポートするソーシャルワーカーやカウンセラーとして活躍しています。専門職以外にも、身につけた心理・福祉の視点や知識、コミュニケーション能力を生かし、さまざまな分野での幅広い活躍が期待されています。めざせる職種・業界
- ソーシャルワーカー
- カウンセラー
- 介護支援専門員
- 公務員(福祉職・心理職・一般職)
- 社会福祉施設(児童・障がい者・高齢者)
- 社会福祉協議会
- 病院 など
就職実績(2025年5月1日現在)
- 医療、福祉
- 卸売業、小売業
- 公務
- 金融業、保険業
- サービス業
- 製造業
- 建設業
- 情報通信業
- その他
主な就職先(2025年3月卒業生)
- 社会福祉法人山水苑
- 社会福祉法人けやきの杜
- 社会福祉法人関耀会
- 児童養護施設 臨海学園
- 社会福祉法人上の原学園
- 社会福祉法人朝日会 愛の里
- 日立市社会福祉協議会
- 茨城県商工会連合会
- 日立市社会福祉事業団
- 茨城県信用農業協同組合連合会
- 日立総合病院
- 土浦協同病院
- 高萩協同病院
- 筑波メディカルセンター病院
- 日本調剤(株)
- (株)日立ドキュメントソリューションズ
- (株)ケーズホールディングス
- 茨城県(福祉職)
- ひたちなか市役所
- 東海村役場
- いわき市役所
卒業生の声

実習先で知ったICの学びの充実度。
その成果が社会福祉士試験合格につながる
黒澤 泰
専門:家族心理学/人間関係論/臨床心理学
心理福祉学科 教員

清原 舞 生活科学部 心理福祉学科 教員

岩﨑 眞和 生活科学部 心理福祉学科 教員


心理福祉学科の教員一覧
高度な専門性と、豊富な現場経験を兼ね備えた教員は、学生の飛躍的な成長を支える原動力。成績優秀なだけではない、他者に寄り添い支えられる、真に優れた人材の育成に向けて、大学全体でチームワークを組み、持てる力の限りを尽くして取り組んでいます。