多文化協働クリエイター認定科目公開講座「外国人児童生徒支援演習」を開催しました
4日間全15回の講座の様子をご紹介いたします。
多文化協働クリエイターの紹介や公開講座概要はこちらから
第1回:10月5日(土)
.jpg)
授業担当:中山健一先生(文学部文化交流学科教授)
第1回は、本学が独自で認定する”多文化協働クリエイター”の言葉にも使われている「多文化」「協働」等の言葉の確認から始まりました。
その後、日本語教育・日本語学習支援に視点をあて、自分が外国語を勉強するときにわかりやすい授業とはどんなものだったか、日本語の構造を学び、団体、学校等が発行している日本語の教科書を見比べながら日本語にどんな練習が必要とされるかについて考えるワークを実施しました。
.jpg)
学生の感想(抜粋
- 講座を聞いて、日本語教育が身近にあることを感じた。生活者として共に地域で暮らす住民として一支援ができると共存しやすくなると感じた。
- 日本語の教科書を見たり、自分が外国語を学ぶ立場で考えたりすることを通して言語学習において文法と会話の両方が大切なのだと学んだ。
第2回:10月26日(土)
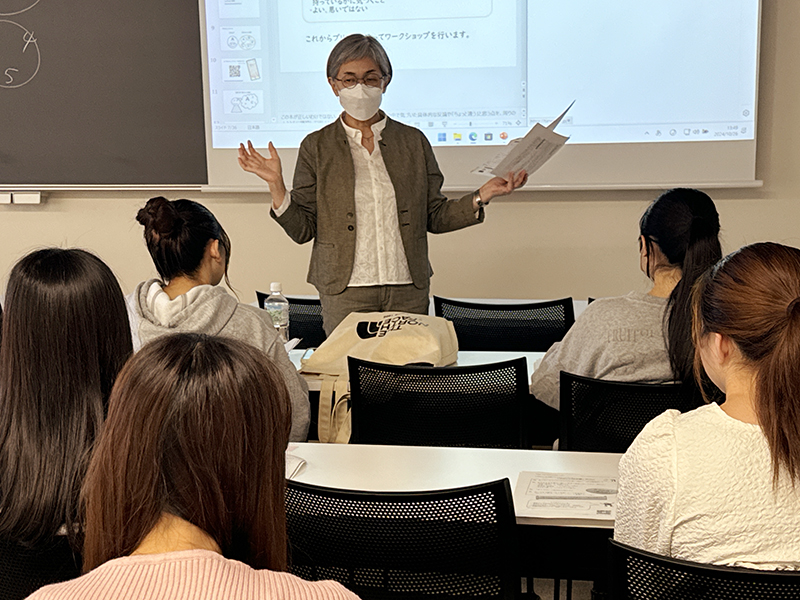
授業担当:山田野絵先生(兼任講師)
ボランティア団体として外国人(日本語が母語ではない人)の方に日本語支援をされている山田先生の講座では、「やさしい日本語」「やさしい傾聴」の仕組みやコツを解説いただいたのち、先生が考案した「やさしい日本語コミュニケーション」の実践を通じて、言葉や文化、考えの異なる方々への態度について考える機会が多く用意されました。
日本語が母語でない方以外にも、子供や高齢者、障害者などの方に対し、「やさしい日本語」や「やさしい傾聴」が非常に有用であることと同時に、相手のアイデンティティを尊重して応対する「態度」が大切であることを学んだようです。
日本語が母語でない方以外にも、子供や高齢者、障害者などの方に対し、「やさしい日本語」や「やさしい傾聴」が非常に有用であることと同時に、相手のアイデンティティを尊重して応対する「態度」が大切であることを学んだようです。

学生の感想(抜粋
- やさしい日本語は外国の方だけではなく、日本人にも大きなメリットがあることが分かった。
- 文化的アイデンティティの学びでは、1つの答えや決まりに固執せずに、みんな違ってみんな良いという寛大な心を持てるといいと思った。どうしても1つに絞らなくてはならない事柄は、多数決でなくみんなで対等に話し合いを重ねてオリジナルの1つのものをだしていけたらよいのではないかと思った。
- アルバイト先で外国人のアルバイト生やお客さんと接する際、英語を使ってコミュニケーションを図っていたが、うまく伝わらないこともあったのでやさしい日本語を使って対応をしてみたい。
第3回:11月9日(土)
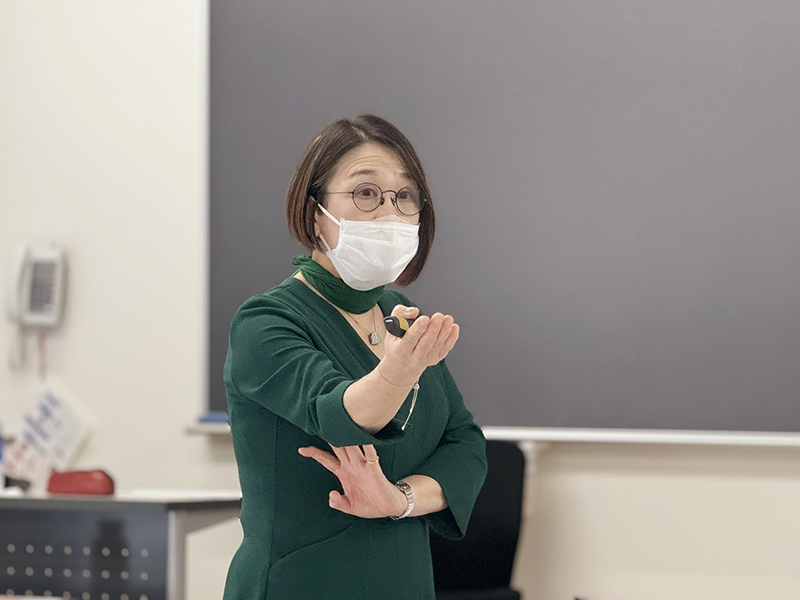
授業担当:仙波美哉子先生(外部講師/文部科学省地域日本語教育アドバイザー・茨城県地域日本語教育推進員)
仙波先生は肩書にあるとおり、茨城県で外国人への日本語支援の輪を広げる様々な活動をされているため、茨城県内に在留している外国人の数とその方々を支援する体制や数の報告から講座がスタート。その後、外国人児童生徒の日本語支援の課題と題し、これまで先生が対応してきた外国人家族の事例が提示されました。家庭環境やその家族の背景にあるものを想像しながら、児童生徒を支援する方法を検討するワークとして、受講者は自分が思い描く将来の姿(職業)で前述の方々を支援するにはどうするかを模索しました。

学生の感想(抜粋
- 子どもたちの支援のケースについて、幼稚園児~高校生やその保護者は様々な悩みを抱えていること、そして私たちは、その子どもたちや保護者が相談しやすい環境を作っていくことが改めて大切だと思った。
- 外国人児童生徒が増えており、その一つ一つと完璧に向き合うことは難しくなると思うので、支援員や相談員、相談相手となれる人材が必要不可欠だと思った。この社会(多文化共生社会)で立派な構成員として生活するための術を学べたように思うので復習をし、正しい知識をさらに身につけたい。
- 子と親(外国人家庭)をセットで考えて対処するというのは盲点だった。目で見えない問題にも目を向けることは難しいが、日本人として、生活者として気にかけていく必要性を感じた。
第4回:11月30日(土)

授業担当:勝山紘子先生(文学部文化交流学科助教)
最終回の講座は、山田先生の講座の展開編として日本人向けに作られている文書を要支援者向けに作成する等のワークを実施。勝山先生も外国人への日本語支援をされている経験から、こどもの入園・入学準備の手続き等、重要な案内をどのように置き換えれば日本語の不得意な外国人保護者に伝わるのかを学生と一緒に考えながら進めていきました。
また、受講者は文学部や生活科学部の学生で構成されており、それぞれの異なる学科で培った学びと多文化共生、多文化協働を掛け合わせて考える機会にもなったようです。
また、受講者は文学部や生活科学部の学生で構成されており、それぞれの異なる学科で培った学びと多文化共生、多文化協働を掛け合わせて考える機会にもなったようです。

学生の感想(抜粋
- 近年、日本に住む外国人が増えている中、日本人がコミュニケーションを諦めてしまうというのは(英語ができないからといって)外国人にとってとても悲しく辛いことであると思うため、もっとやさしい日本語が広がり、本当の意味で多文化共生、多文化協働をしていけたら良いなと思った。
- やさしい日本語を学んで、自動翻訳や相手の言語にするということが必ずしも正しい選択ではないことを知った。機械ではなく、人が伝えることで対人(たいひと)への思いやりだったり、コミュニケーションだったりの場所の一つになると感じた。
15回の講座を通じ、受講者の"多文化協働"に対する認識や考えを深める機会となったことと思います。
私たちもすべての方が共に暮らせる社会を願って次年度も同講座を開催します。ご興味のある方はぜひご応募ください。
※募集に関する情報は2025年夏頃、大学HPで公開します。
地域・国際交流センター
地域交流課について
地域交流課では、学生ボランティアの他にも地域に貢献できる講習や講演会を企画しています。
地域社会との連携、地域活動のほかに、公開講座・県民大学など各種講座運営、聴講生に関すること、広報誌「みどりの」編集・発行、地域・教育ボランティアに関することを担当しています。
気になる方は、地域・国際交流センターまでお問い合わせください。
茨城キリスト教大学の掲げる地域連携方針はこちらからご案内しています。
取扱窓口時間
平日 8:45〜16:45
※昼休み時間もオープンしています。
土曜日 8:45〜11:50
※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。
※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります
※昼休み時間もオープンしています。
土曜日 8:45〜11:50
※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。
※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります

