【COC+事業】幼児保育専攻開設15周年記念講演会:西巻 茅子【わたし・絵本・子ども『子どものアトリエ 絵本づくりを支えたもの』の周辺】のご報告
2019年6月15日土曜13時半~15時、本学8101教室にて、絵本『わたしのワンピース』の作家西巻茅子さんの講演会が行われました。西巻さんの本づくりを、編集者として40年にわたって支えてきたこぐま社の関谷裕子さんが質問し、西巻さんが答える、お二人の対談の形で、絵本や子どもに寄せる想いを率直に語っていただきました。親・子・孫三代にわたる西巻ファンや、幼児教育の場から、また本学学生・教職員など、約200名が「子ども」と向き合い、楽しく充実したひと時を過ごしました。
東京芸術大学工芸科を卒業後、絵画教室「子どものアトリエ」を開き、集中してよい絵を描く幼い子どもたちに出合った西巻さん。1968年に日本版画協会展新人賞奨励賞を受賞した西巻さんの作品が、こぐま社を創設し石版画(リトグラフ)を応用した本づくりを模索していた佐藤英和氏の目に留まりました。手紙をもらって西巻さんがこぐま社を訪ね、ブレーンの人達と会ったのが5月。「何かテーマを決めて描いていらっしゃい」との言葉に、ボタンや裁縫箱の絵を何枚か持っていくと、スタッフの中村成夫さんが、物語としてつながるように考えてくれ、改めて原画を描いて、処女作『ボタンのくに』が出版されたのが8月でした。西巻さんの中に育っていた子どもと絵本への想いが、「世代を超えて読み継がれる絵本を日本の子どもたちに届けたい」という編集者佐藤英和氏の情熱と出会って、一気に形になりました。
こぐま社で佐藤氏が収集した欧米の絵本を見て学ぶうち、当時日本で主流であった、童話や民話に挿絵をつけた絵本ではなく、レオ・レオーニ『あおくんときいろちゃん』(米59年)のような、絵が物語を語る絵本を創りたいと、3作目『わたしのワンピース』のラフスケッチを作りました。ブレーンの人たちから「花畑を通ると、なぜ花模様になるのかわからない、お花が好きだ、花畑を転げまわったなど、理由の解る頁が欲しい」と言われるものの、そういう「意味」をつけるのはいやで、自分の主張を通しました。けれども、ラフスケッチで描いてあった、流れ星になっているうさぎの絵は「地球に激突してかわいそうだ」と言われ、現在の流れ星だけの絵に。今でも、子どもに、この場面で「なんで、うさぎさん、いなくなったの?」と聞かれることがあるそうです。
『わたしのワンピース』は、当初書評で取り上げられることもなく、受賞することもありませんでしたが、5~6年経ったころ、東京子ども図書館の方が、図書館でいつも貸し出し中の「書架にない本」として朝日新聞のコラムで紹介。子ども自身が認めてくれたことがとてもうれしかったそうです。また、その頃から、子どもと本が出合う場にいる大人からも徐々に評価されるようになり、10年たった頃には代表作と認められるようになりました。関谷さんご自身も、どうして子どもが、そんなに『わたしのワンピース』を好きなのかわからなかったが、娘さんに読んであげていたとき、「くさのみって、とっても いいにおい」の場面で娘さんが本をひったくって「あ~ぁ、いいにおい」と息を吸ったことがあって、この本は、子どもにとって、匂いまでする本なのだと、腑におちたとのこと。
西巻さんは、子どもには、いいものとつまらないものを見分ける感受性が備わっていると、おっしゃいます。子どもは、上手とは違う「いい絵」を描く力を持っている。そういう子どもの感受性を、「感受性だけではこの社会でやって行けない」と知っている大人が踏みつぶし、大人の頭にあるいい絵を描かせようとする。「子どものために」「子どもがわかるように」ではなくて、子どもに真正面から向き合って、50年描いてきたとおっしゃいました。 絵本は、作るのも売るのも買うのも大人、でも、読んで楽しむのは子ども。よい絵本をつくるためには、誰に向かって、何のために描くのか、受け取る子どもとのコミュニケーションが不可欠と、編集者の関谷さんはおっしゃいました。
今年、出版50周年を迎え、『わたしのワンピース』は現在188刷、発行部数は178万部を超え、こぐま社を支える読み継がれる本の一冊になっているとのことです。この夏には、神奈川近代文学館で、「『わたしのワンピース』50周年 西巻茅子展—子どものように、子どもとともに」も開催され、新作絵本『いえでをした てるてるぼうず』の出版も予定されています。
戦後日本の絵本づくりの活写された興味深いお話でしたが、読み継がれる絵本とは何か、子どもと絵本を読むことの意味、今という時代に子どもの心と向き合うことの大切さ・難しさを、改めて考える機会になりました。保育者を志す学生たちも思うことの深かった様子です。来場者からも充実した時間が過ごせたという、熱のこもった感想が寄せられました。終了後のサイン会では、西巻さんが、一冊一冊に、ていねいに絵を描いてくださいました。
会場の様子







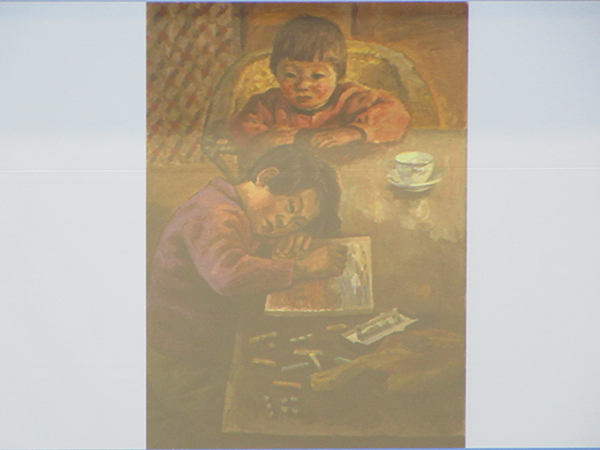










一般の方の感想から
・ お二人の掛け合い、おしゃべりしているような雰囲気が楽しいながらも、鋭い本音を伺って、西巻さんのお人柄に触れた思いでした。子どものとき、一番ドキドキワクワクした印象に残っている絵本「わたしのワンピース」の作家にお会いできて幸せでした。
・ 娘のファーストブックが『わたしのワンピース』です。この講演に来るにあたり、高2の娘と話したら、幼い時に触れた絵本を、よく覚えていて驚きました。絵が展開していく絵本として、この本が作られたということ、子どもは感性でよい本を選ぶというお話、興味深く伺いました。
・ お話を伺っていて、4歳の長女が流れ星のシーンで「うさぎちゃんいなくなっちゃったね」と言っていたことを思い出し、子どもの受け止め方を大切に、これからも一緒にたくさん絵本を楽しみたいと思いました。
・ 初めて『わたしのワンピース』と出会ったのは、大学生の時で、そのときは可愛いなぁとしか思いませんでした。最近、一歳の息子と読んだとき、「なんで、お空を飛んだウサギさんがいないのかな、この星空のページ?」と思いました。その謎が解けてすっきりです。息子はこの本と幼い時に出会えてよかったと、思いました。
・ 幼稚園教諭として、子どもに絵を描かせようとしてしまう自分を振り返る機会になりました。子どもは作家の人間性を感受する力を持っているということ、上手な絵と良い絵は違うということなど、新しい価値観を知ることができました。
・ 時代によって売れる本も売れ方も違うけれど、関谷さんがおっしゃっていた「子どもを通して」絵本を知るということが本質と思いました。大人の事情ではなく、子ども主体で本が評価されるためには、時間をかけて本を揃えていく図書館の役割が大切と思います。
・ 30年前娘に読み聞かせた『わたしのワンピース』を、今、孫に読んでやっています。これからも、時代を超えて読み継がれる本を創り続けてください。
・ 娘のファーストブックが『わたしのワンピース』です。この講演に来るにあたり、高2の娘と話したら、幼い時に触れた絵本を、よく覚えていて驚きました。絵が展開していく絵本として、この本が作られたということ、子どもは感性でよい本を選ぶというお話、興味深く伺いました。
・ お話を伺っていて、4歳の長女が流れ星のシーンで「うさぎちゃんいなくなっちゃったね」と言っていたことを思い出し、子どもの受け止め方を大切に、これからも一緒にたくさん絵本を楽しみたいと思いました。
・ 初めて『わたしのワンピース』と出会ったのは、大学生の時で、そのときは可愛いなぁとしか思いませんでした。最近、一歳の息子と読んだとき、「なんで、お空を飛んだウサギさんがいないのかな、この星空のページ?」と思いました。その謎が解けてすっきりです。息子はこの本と幼い時に出会えてよかったと、思いました。
・ 幼稚園教諭として、子どもに絵を描かせようとしてしまう自分を振り返る機会になりました。子どもは作家の人間性を感受する力を持っているということ、上手な絵と良い絵は違うということなど、新しい価値観を知ることができました。
・ 時代によって売れる本も売れ方も違うけれど、関谷さんがおっしゃっていた「子どもを通して」絵本を知るということが本質と思いました。大人の事情ではなく、子ども主体で本が評価されるためには、時間をかけて本を揃えていく図書館の役割が大切と思います。
・ 30年前娘に読み聞かせた『わたしのワンピース』を、今、孫に読んでやっています。これからも、時代を超えて読み継がれる本を創り続けてください。
文学部児童教育学科幼児保育専攻学生の感想から
・ 絵画教室の仕事では「お金以上に。子どもの描くすばらしい絵から得るものがあった」「集中して一枚をしっかり描く子どもはよい絵を描く」と聞いて、はじめは「よい絵とはどんな絵なのだろう?」と思ったが、講演を聞くうちに、西巻さんが絵本づくりで大切にしていらしたものが伝わってきて、よい絵は理屈ではなくて、心で見て感じてわかるものなのではないかと思った。今まで授業などで、昔から読み継がれてきたよい絵本について学ぶ機会はあったが、自分では、どうしてその本が長い間読み継がれて来たのか、他の本と何が違うのか、疑問に思っていたところもあったので、自分の心の目で見て感じてその本たちを含めて、たくさんの絵本を楽しみたいと思った。(2年生)
・ 『わたしのワンピース』の夜の場面で、うさぎが居なくなって星だけが流れていくのを見たとき、「うさぎはどうしたのだろう」とひっかかった記憶があったので、編集の段階でそうなったと聞いて驚いた。本当の読者は子どもだけれど、絵本をつくるのも買うのも大人という事実と葛藤を目の当たりにした思いがした。大人目線で絵本を選びがちだけれど、子どもの目線で選べるようになりたい。(2年生)
・ 実習準備で絵本を選んだ際に、自分としては子どもの喜びそうな内容や絵を選んだつもりだったけれど、大人の感性で選んで子どもに押し付けてしまっていたのではないかと、反省した。子どもが本当に「おもしろい」と感じる絵本を選べるようになるためには、子どもたちに様々な絵本を読み聞かせして、子どもの生の反応を感じ取っていくことが大切なのだろうと思った。(3年生)
・ 保育所の実習で、子どもに絵を描いてもらった時、絵の表情や色使いが一人ひとり違って個性的なのを見たが、子どもが描き終わったとき、私は褒めながらアドバイスをしてしまった。講演を聞いて、子どもが全力を出し切って完成したものに、アドバイスするのは違うかなと考えさせられた。絵から匂いを感じるような子ども特有の感性を受け止め、子どもがのびのびと描けるような接し方ができるようになりたいと思った。(3年生)
・ 西巻さんのように自分の考えをしっかり持って、たとえその考えが、なかなか認められない時でも、貫き通せるような、こだわりを持った大人になりたいと思った。(3年生)
・ 関谷さんのお子さんが絵本から、草の実の香を感じていたというエピソードを伺い、絵本を子どもと読むことで、新たな絵本の面白さや驚きを発見でき、子どもの感受性や考え方が解るのだろうと思った。子どもと関わる職に就きたいと思っているものとして、子どもと同じ目線で物事をとらえ、気持ちを受け止め、子どもの可能性を伸ばしていけるよう、学びを深めていこうと思う。(4年生)
・ 『わたしのワンピース』の夜の場面で、うさぎが居なくなって星だけが流れていくのを見たとき、「うさぎはどうしたのだろう」とひっかかった記憶があったので、編集の段階でそうなったと聞いて驚いた。本当の読者は子どもだけれど、絵本をつくるのも買うのも大人という事実と葛藤を目の当たりにした思いがした。大人目線で絵本を選びがちだけれど、子どもの目線で選べるようになりたい。(2年生)
・ 実習準備で絵本を選んだ際に、自分としては子どもの喜びそうな内容や絵を選んだつもりだったけれど、大人の感性で選んで子どもに押し付けてしまっていたのではないかと、反省した。子どもが本当に「おもしろい」と感じる絵本を選べるようになるためには、子どもたちに様々な絵本を読み聞かせして、子どもの生の反応を感じ取っていくことが大切なのだろうと思った。(3年生)
・ 保育所の実習で、子どもに絵を描いてもらった時、絵の表情や色使いが一人ひとり違って個性的なのを見たが、子どもが描き終わったとき、私は褒めながらアドバイスをしてしまった。講演を聞いて、子どもが全力を出し切って完成したものに、アドバイスするのは違うかなと考えさせられた。絵から匂いを感じるような子ども特有の感性を受け止め、子どもがのびのびと描けるような接し方ができるようになりたいと思った。(3年生)
・ 西巻さんのように自分の考えをしっかり持って、たとえその考えが、なかなか認められない時でも、貫き通せるような、こだわりを持った大人になりたいと思った。(3年生)
・ 関谷さんのお子さんが絵本から、草の実の香を感じていたというエピソードを伺い、絵本を子どもと読むことで、新たな絵本の面白さや驚きを発見でき、子どもの感受性や考え方が解るのだろうと思った。子どもと関わる職に就きたいと思っているものとして、子どもと同じ目線で物事をとらえ、気持ちを受け止め、子どもの可能性を伸ばしていけるよう、学びを深めていこうと思う。(4年生)
地域・国際交流センター
地域交流課について
地域交流課では、学生ボランティアの他にも地域に貢献できる講習や講演会を企画しています。
地域社会との連携、地域活動のほかに、公開講座・県民大学など各種講座運営、聴講生に関すること、広報誌「みどりの」編集・発行、地域・教育ボランティアに関することを担当しています。
気になる方は、地域・国際交流センターまでお問い合わせください。
地域社会との連携、地域活動のほかに、公開講座・県民大学など各種講座運営、聴講生に関すること、広報誌「みどりの」編集・発行、地域・教育ボランティアに関することを担当しています。
気になる方は、地域・国際交流センターまでお問い合わせください。
取扱窓口時間
平日 8:45〜16:45
※昼休み時間もオープンしています。
土曜日 8:45〜11:50
※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。
※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります
※昼休み時間もオープンしています。
土曜日 8:45〜11:50
※日・祝及び大学指定の休日等は閉室となります。
※学内行事等の事由で閉室日・閉室時間が変更になる場合があります

